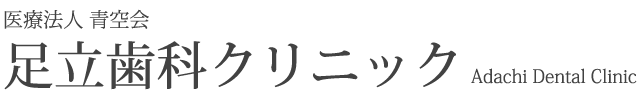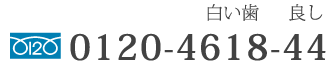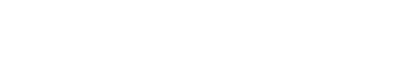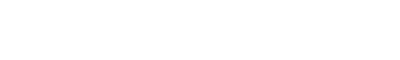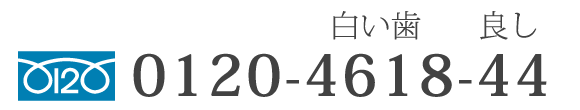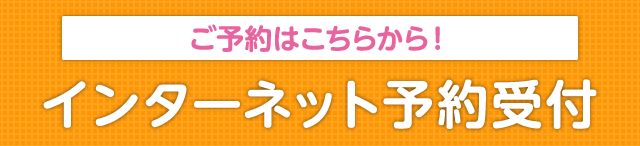親知らずがある人は口内炎ができるって本当?理由や注意点を解説
スタッフブログ 2024.06.07

気を付けているつもりでも親知らずの周辺に口内炎ができてしまうことはありませんか。口内炎ができると痛みもありますし、食事のときの不快感もありどうにかしたいと思うものですよね。
親知らずと口内炎は一見、関係のないもののように思っているかもしれません。
実は、親知らずの状態によって口内炎ができてしまうことがあります。その理由や、注意点について、詳しく説明していきたいと思います。
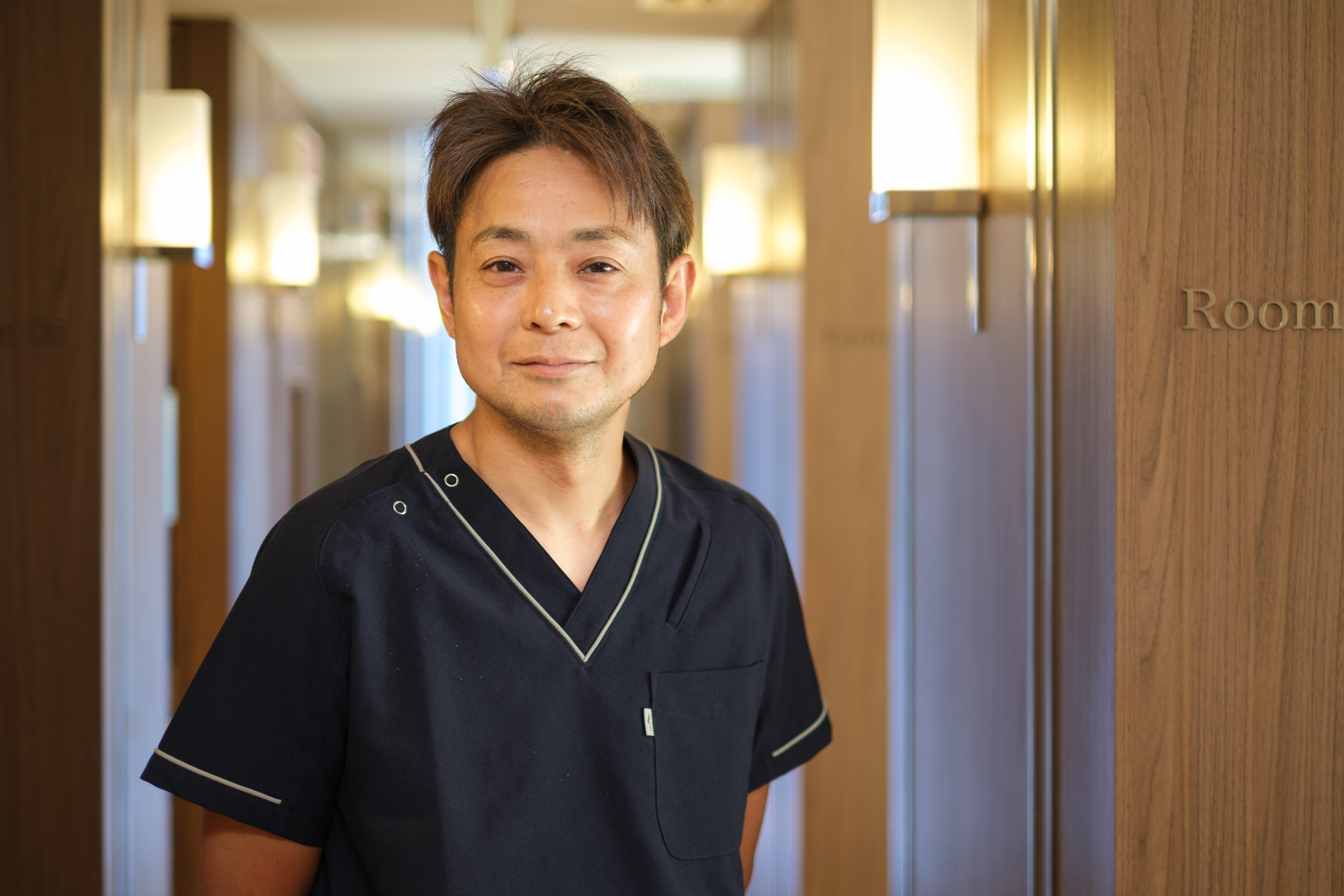
監修者情報
医療法人 青空会 足立歯科クリニック 院長
足立 哲也(あだち てつや)
プロフィール
大阪歯科大学を卒業後、幅広い年齢層の患者と向き合いながら、むし歯や歯周病、予防歯科などの診療に取り組む。
患者が安心して通えるよう、丁寧なカウンセリングとやさしい対応を心がけている。
略歴
- 平成11年3月 朝日大学歯学部卒業
- 平成11年4月 大阪歯科大学研修医
- 平成12年4月 中岡歯科医院勤
- 平成15年4月 足立歯科クリニック開業
- 平成16年12月 医療法人青空会理事長
- 平成22年9月 南カリフォルニア大学ジャパンプログラム卒業
- 平成23年3月 AAID(アメリカインプラント学会)マキシコース卒業
- 平成24年4月 ICOIコロンビアコース
- 平成25年6月 インディアナ大学 インプラントコース
- 平成30年3月 大阪歯科大学院卒業
- 令和2年4月 大阪歯科大学 非常勤講師
所属学会・資格
- ADIA(アメリカインプラント学会)認定医・専門医
- IDIA国際歯科インプラント学会
- 日本口腔インプラント学会認証医・専門医
- ICOI国際口腔インプラント認定医・指導医
- AAID(アメリカインプラント学会)認定医・専門医
- 日本顎咬合学会認定医
- 南カリフォルニア大学 客員研究員
- 南カリフォルニア大学 ジャパンプログラムリーダー
- インディアナ大学 口腔再生学講座 インプラント研究科 客員講師
- インディアナ大学歯学部 日本歯科矯正プログラム 認定医
- 歯科医師臨床研修指導医
- 歯科放射線学会 認定医
- 口腔医科学会 認定医・専門医
- オステムインプラント 指導医・公認インストラクター
- 光機能化バイオマテリアル研究会会員
- JAID代議員
- 国際審美学会会員
- 臨床器材研究所認定医
- 介護支援専門員(ケアマネージャー)
- 衛生検査技師
- BLS認定医
- 福祉住環境コーディネーター
- ISOI国際口腔インプラント学会ドイツ口腔インプラント学会日本支部
そもそも口内炎とは

口内炎は誰でも一度は経験した事のあるような、ポピュラーなものです。
口の中の粘膜に起きる炎症としても知られており、頬の内側だけでなく舌や唇などにできることも少なくありません。
炎症を起こすと痛みを伴うようになり食事や寝ているときにも不快感を覚えるようになります。
口内炎には大きく分けて2種類あります。
・アフタ性口内炎
・カタル性口内炎
それぞれ説明したいと思います。
アフタ性口内炎
口内炎でも、円形のものや楕円で白っぽいできもののようなものをアフタ性口内炎といいます。最もポピュラーなものになり、粘膜の環境の乱れが要因です。
口腔内にはたくさんの常在菌がいますが、対抗するために粘膜を守る因子が働いています。バランスを粘膜が保っているのですが、食事や疲れ、ストレスによって症状が出てしまうこともあります。
カタル性口内炎
外傷性口腔内ともいわれているものになり、粘膜の部分に赤い炎症が出来水ぶくれになっている状態です。
ひりひりとした痛みを感じやすいといわれており、症状が悪化すると全体的に腫れているような状態になります。
口内炎の嚙み合わせによる物理的な刺激や、虫歯や入れ歯の影響、火傷なども考えられます。一度や二度であればカタル性口内炎にはなりませんが、何度も行うことで症状が悪化します。
まずは、どちらの口内炎なのかを歯科医院を受診したうえで確認しましょう。
親知らずの周辺に口内炎ができる理由

親知らずの周辺に口内炎ができる理由から説明していきたいと思います。
・頬っぺたを無意識で噛んでしまう
・親知らずの生え方に問題がある
それぞれ説明したいと思います。
頬っぺたを無意識で噛んでしまう
親知らずが生え、噛み合わせが悪くなることで頬っぺたを噛みやすくなってしまいます。頻繁に噛んでしまうと、炎症を起こし口内炎となります。
親知らずは個人差があり、15歳前後で生えますが、なかには20歳を過ぎてから親知らずが生える人もいます。永久歯の後に生えてくるため、それまでは歯並びがきれいだったのに、親知らずが生えて崩れてしまうケースも少なくありません。
特に、もともと顎が小さい人の場合は、歯のアーチが圧迫されるようになり歯同士が重なってしまうことも考えられます。頬っぺたを無意識で噛んでしまう人は、親知らずが影響していることもあります。
親知らずの生え方に問題がある
親知らずが斜めに傾いて生えてしまう人もいます。本来まっすぐであればそこまで気にすることはないのですが、斜めに生えることで頬の粘膜を刺激してしまいます。
親知らずの生えるスペースが十分に取れていないことが原因だといわれており、斜めや横に生える事で歯茎に負担をかけてしまっている可能性も考えられます。
特に現代人は親知らずがまっすぐに生えにくいといわれており、斜めや横向きが増えています。親知らずが虫歯になると余計に傷つけやすくなってしまうため、早めに処置が必要になってきます。
口内炎を治すためにはどうしたらいいの?

口内炎があると、つい気になって舌で触ってしまう人もいると思います。
口腔内にあるトラブルは思っている以上に不快なものですし、できるだけ早く治したいものですよね。
親知らずを治すための方法にはこのようなものがあります。
・免疫力を低下させない
・触らないようにする
・軟膏をつけて様子を見る
・うがいや内服薬を使う
・レーザー照射による治療
・親知らずの抜歯を検討する
それぞれ紹介します。
免疫力を低下させない
口内炎は親知らずの噛み合わせ以外にも、免疫力が低下するとできやすくなります。一時的に治ったとしても何度も口内炎ができてしまうので、免疫力を高める工夫も行うようにしましょう。
例えば、食事の栄養バランスに気を付けてビタミンやミネラルをしっかりと摂ること。睡眠時間や休息を意識的にとるようにして体の調子を整えていきましょう。
免疫力を低下させないのも、口内炎を治すためには重要なポイントになります。
触らないようにする
口内炎があると、つい気になって触ってしまう人も少なくありません。
舌や指で触るとなかに黴菌が入ってしまったり炎症を起こす原因となります。
口内炎は刺激によってもできるので、気になるかもしれませんが、極力触らずに様子を見るようにしましょう。
軟膏をつけて様子を見る
一般的な口腔内であれば、1週間程度で症状が落ち着き自然と治ります。そのため、市販薬の軟膏を使って様子を見ている人も多いのではないでしょうか。
2週間経っても状況が改善されないときは、口内炎ではない可能性も考えられます。
例えば、口腔がんでは同じ場所に口内炎ができ、2週間以上治らないときや痛みを感じることがあります。放置するのではなく口腔外科も行っている歯科医院に相談し、状況を確認してもらうようにしましょう。
うがいを使う
口内炎の治療の基本はうがいになり、市販のうがい薬を使う方法もあります。
殺菌消毒効果の高い「イソジン」や、殺菌効果入りの「マウスウォッシュ」も使えます。
水うがいでも正しいやり方を知っていれば、口内炎にはおすすめです。
まず、ブクブクうがいをして、次に上を向きガラガラうがいをする方法です。
うがい液のなかには炎症を抑える成分が含まれているものもあります。
また、局所麻酔が使われ痛みを軽減するようなうがい液を使う場合もありますが、症状の原因によって「抗ウイルス薬」を内服して治す場合もあります。
まずは、口内炎の原因をはっきりさせたうえで最適なものを選び治すようにしましょう。
レーザー照射による治療
何度も繰り返す口内炎には、レーザー治療を行う場合もあります。直接レーザーを照射して、粘膜の表面部分にかさぶたを作ります。
3分程度の短時間で治療ができますし、治療後に痛みが続くこともありません。口内炎の痛みを和らげ、炎症を抑える効果が期待できます。
どの程度の口内炎なのかによっても変わりますが、1回もしくは2回程度通います。保険適用外になることもありますので、確認しておくのをおすすめします。
親知らずの抜歯を検討する
軟膏をつけても改善されず、その原因が親知らずにある場合は、抜歯を検討するのをおすすめします。
親知らずは頬っぺたもしくは歯茎に当たっていることで傷つけてしまっている可能性があります。口内炎が治ったと思っても頻繁に繰り返してしまう状態では、日常生活に支障が出てしまうことも考えられます。
親知らずを残すよりも抜歯してしまう方法もあります。特に親知らずの向きが斜めや横向きの場合は歯並びにも影響します。親知らずの抜歯を検討してみるのも一つの方法としておすすめです。
まとめ
口内炎ができると、食事など日常生活にも影響してしまいます。その原因が、親知らずの生え方にあるとは、考えていない人もいるのではないでしょうか。
親知らずが横向きや斜めになっていると、歯並びはもちろん、ブラッシングが行き届かなくなり虫歯や歯周病のリスクも高めてしまいます。口内炎を何度も繰り返している人は、早めに相談するのをおすすめします。